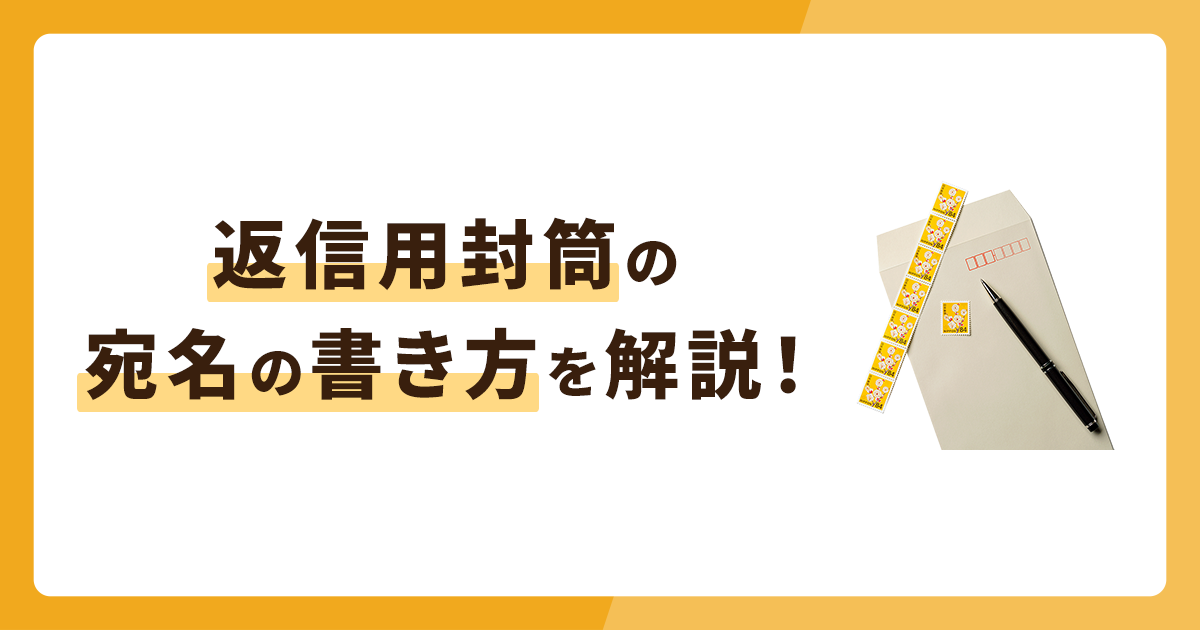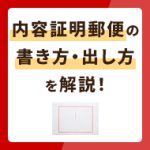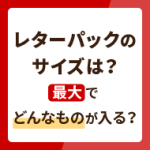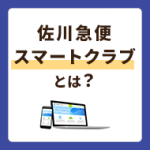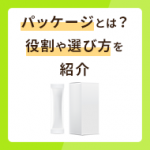取引先から書類を返送してほしいときや、就職活動の際、企業に書類を返送する際などに利用することの多い返信用封筒。
返信用封筒は一般的な手紙やはがきよりも利用する頻度が比較的少ないため、返信用封筒の正しい書き方やマナーをよく知らないという人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、返信用封筒の正しい宛名の書き方や、返信用封筒を返す際のマナー、返信用封筒を同封する際によくある疑問について解説します。
返信用封筒の宛名の書き方
返信用封筒を利用する大きなメリットはおもに以下の3点が挙げられます。
- 相手が返信のための封筒を準備する手間が省ける
- 返送してほしい書類がより早く返送される可能性がある
- 相手による返送先の記載ミスが防げる
このように、返信用封筒が同封されていると、相手に丁寧な印象を与えられるだけではなく、スピーディーかつ確実に書類のやりとりが行えます。
以下では、返信用封筒の選び方や宛名の書き方などを詳しく解説します。
封筒の選び方
返信用封筒には、シンプルな茶封筒や白色の封筒を使用することが一般的です。ただし、社名やロゴなどが入った専用封筒があればそちらを使用することが多いでしょう。
返信用封筒のサイズに規定はありません。しかし、次の2点をポイントにして選ぶとよいでしょう。
- 封入する書類を折ってよいか、よくないか
- 書類の量が少ないか、多いか
封入する書類が折ってよいものであれば、定形封筒の長形3号封筒を使用することが多いでしょう。長3封筒のサイズは約120mm×235mmで、Ā4用紙を三つ折りにして入れることができます。
さらに小さいサイズでは長形4号封筒もあります。長形4号封筒のサイズは約205mm×90mmで、B5用紙を三つ折りにして入れることが可能です。
一方、封入する書類が折り曲げ厳禁の場合は、A4用紙が折らずに入る角2(かくに)封筒を使用することが多いでしょう。なお、角形2号封筒のサイズは約240mm×332mmです。
また、B5用紙を入れる場合は角形3号封筒も使用できます。角形3号封筒のサイズは約216mm×277mmです。
相手が書類を入れようとしたときに、スムーズに書類を入れられることを考慮しながら、書類の内容や枚数によって適切なサイズを選びましょう。
住所の書き方
返信用封筒は、相手が自分に宛てて送ることを目的とした封筒ですので、封筒の表には以下の内容を記載しておきます。
- 自分の住所の郵便番号
- 住所
- 会社名(あれば)
- 氏名
会社名を書く場合は、(株)(有)のように省略をせず、「株式会社」や「有限会社」のように正式名称で書きましょう。
また、縦書きの場合、番地や部屋番号の数字は算用数字ではなく漢数字を使用することがマナーです。横書きの場合は算用数字でも漢数字でも問題はありません。
なお、基本的に裏面には送り先(相手)の住所を書く必要はなく、白紙で問題ありません。
「宛と行」どちらを書くか
一般的な手紙やはがきでは、「〇〇様」「株式会社△△御中」といった宛名の書き方をしますが、返信用封筒の場合は、「〇〇行」「株式会社△△行」のように「行」を使うことが一般的です。
「〇〇宛」「株式会社△△宛」と記載することもありますが、ビジネスシーンでは「行」を使う方が適切といわれています。ただ、「宛」と書いても非常に失礼にあたるということはなく、どちらでなければいけないという決まりはありません。
切手の選び方・貼り方
返信用封筒には、量機運受取人払郵便のような場合を除き、封筒に切手を貼っておきましょう。切手の貼り忘れはマナー違反になるため注意が必要です。
返信用封筒で多く使われる封筒の切手の料金は2023年6月現在、次のようになっています。
| 封筒のサイズ | 内容 | 重さ | 料金 |
| 長形3号・長形4号 | 定形郵便 | 25gまで | 84円 |
| 50gまで | 94円 | ||
| 角形2号・角形3号 | 定形外郵便 (厚さ3cm以内の規格内の場合) |
50gまで | 120円 |
| 100gまで | 140円 | ||
| 150gまで | 210円 | ||
| 250gまで | 250円 | ||
| 500gまで | 390円 | ||
| 1kgまで | 580円 |
何円分の切手を貼るかは、あらかじめ返送してほしい書類の重量を計り、決めるとよいでしょう。ただし、領収書や証明書類など、何かほかの書類を貼付する可能性もあるため、多めの切手を貼っておくと安心です。
切手を貼る位置は、封筒を縦に使う場合、封筒の左上部分(左から35mm×上から70mm程度の間)が理想的です。封筒を横に使う場合は不当の開封口や郵便番号欄が右側に来るようにした上で、封筒の右上部分(左から35mm×上から70mm程度の間)に切手を貼りましょう。
封筒の入れ方・折り方
長形3号封筒に長形4号封筒を入れたり、長形角形2号の封筒に角形3号の封筒を入れるような場合は返信用封筒を折る必要はありません。
しかし、送付用封筒と返信用封筒のサイズが同じ場合のように、返信用封筒が入らない場合は返信用封筒を折っても問題はありません。
封筒を折る場合は、返信用封筒であることがわかるように、自分の宛名を記載した面が上向きになるように3つ折りにして入れるとよいでしょう。
同封された返信用封筒を返すとき
ここまで返信用封筒を送る方法を紹介してきましたが、ここからは返信用封筒が同封されていたときの返し方を解説します。
返信用封筒を返す時は、そのまま封筒に書類を入れて送るのではなく、宛名部分を修正する必要があります。
返信用封筒には「〇〇行」「株式会社△△宛」など、宛名部分に「行」や「宛」が書かれていますが、縦書きの場合は縦線2本で、横書きの場合は横線2本で消しましょう。
そして、縦書きの場合は二重線で消した左側に、横書きの場合は二重線で消した右側に、個人宛であれば「様」、法人宛であれば「御中」と書くことがマナーです。
ただし、書くスペースがない場合は宛名の近くであれば問題ありません。
また、返信用封筒の裏面には自分の住所や名前などを記載しましょう。この場合も、自社名であっても(株)や(有)などとは書かず、「株式会社」や「有限会社」などの正式名称で記載します。
数字は、縦書きでは漢数字で、横書きでは漢数字か算用数字のいずれかで書くことがマナーです。
返信用封筒を同封するときのよくある質問
返信用封筒は業務で日常的に使用する人もいれば、めったに使ったことがないという人も少なくありません。
ここからは、返信用封筒を同封する際に疑問に思いがちなよくある質問について回答します。
返信用の封筒を速達にしたい場合はどうする?
相手からなるべく早く返信が欲しい場合は、返信用封筒を速達で送れるように変えることが可能です。
返信用封筒を速達で送る場合のポイントは、以下の2点です。
- 速達料金分の切手を貼る
- 封筒の表面に赤線を入れる
手紙の場合、例えば重量が250gまでの場合は基本料金に260円をプラスした切手を貼ります。
赤線をつける位置は、縦長の封筒の場合は右上の端、横長の封筒の場合は右下の端に選を引きます。
ただし、赤線をつけ忘れていたり、料金不足の場合は速達で届かない可能性もあるため注意が必要です。
切手は想定料金よりも多めに貼ってもいい?
先に紹介したとおり、返送を希望する書類以外にも、場合によっては添付書類や必要書類が必要となり、返信用封筒の重要が想定より重くなる可能性があります。そのため、切手は想定される最低の料金よりも多めに貼っておいたほうが、料金不足で返送される心配がないでしょう。
郵便物の料金は重量ごとに段階的に決められているため、切手を多めに貼るのであれば、想定料金よりも一段階あるいは二段階上など、重量に応じた料金の切手を貼りましょう。
なお、手紙に貼る切手の枚数には制限はありませんが、貼られる切手の枚数が多すぎると「余った切手を寄せ集めて貼った」という印象を与えかねないため注意が必要です。
御中を使うのはどんなとき?
返信用封筒の行を二重線で消したあと、縦書きの場合は左側に、横書きの場合は右側に、「御中」と書きますが、これは法人の場合や、担当者が不明の場合に使用します。担当者が不明の場合は「ご担当者様」と書いても問題ありません。
なお、個人宛の場合は「御中」ではなく「様」を使いましょう。
まとめ
返信用封筒は、ビジネスや就職活動で利用されることが多いです。例えば宛先が「行」になっているまま返送してしまうと、ビジネスマナーを知らない人と受け止められてしまう可能性もあります。また、返信用封筒を送る場合も、書類がきちんと入るサイズや料金不足にならないように注意が必要です。
返信用封筒の使い方やマナーはそれほど難しいものではありません。お互いが気持ちよく返信用封筒を利用できるよう、あらかじめ正しいマナーを理解しておきましょう。
ダンボールワンではダンボールだけではなく、様々な種類の梱包用品をはじめ、返信用封筒に最適な各種封筒も豊富に取り揃えています。封筒選びでお悩みならぜひ「ダンボールワン」の公式サイトをチェックしてみてください。定番サイズをはじめ、全330点からご希望にぴったりの封筒をお選びいただけます。